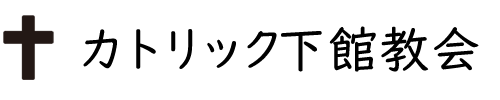時を経て気づくもの
●ヨハネ20・1-9
カトリック下館教会司祭 本間研二
外はまだ闇に包まれ、深い眠りに落ち込んでいた頃、電話が鳴った。母が入居していた施設からで母が亡くなったとの知らせである。いつかこの日が来ると覚悟はしていたが一瞬心が凍った。
葬儀ミサが終わり、長く一人暮らしをしていた母の持ち物をいくつかの段ボール箱に入れ、司祭館に運び込んだ。せわしなく詰め込んだから一度整理せねばと思いつつもなかなか箱を開けることができない。ものぐさのせいではない。あらためて母が生前に着ていた服や日々使っていた物を見ることが、母の死の確認作業をするようで躊躇していたのだ。
数か月後ようやく箱を開く決心をして整理を始めていくと、日々の出来事が記されている一冊のノートが出てきた。ページをめくると至るところに私を案ずる思いが綴られている。息子がいくつになっても、司祭になっても心配は尽きなかったのだろう。短く飾り気のない文面は私の心に沁みた。生きていた時には気づかずにいた母の思いが時を超えて気づかされる。人とは愚かな生き物だ。しばしば大切なことはその時ではなく、時を経て気づかされるのだ。
イエスと寝食を共にして労苦を分かち合った弟子たち。彼らはイエスを心から慕っていた。「主よ、ご一緒なら、牢に入っても死んでもよいと覚悟しております」(ルカ22.33)との言葉に偽りはなかっただろう。あの時までは・・・。
あの日イエスはユダヤ人たちに拘束され、唾をかけられ、鞭打たれ、十字架の上で罪人として殺された。あんなに勇ましかった弟子たちは、そのとき誰一人としてイエスを助けようとはせず、その場を逃げ去ってしまったのだ。
イエスを見捨てた自分たちの臆病さ不甲斐なさによる自己嫌悪と、裏切り者の後ろめたさから、弟子たちはイエスとの間に石のような重い隔たりが立ちふさがったと感じたに違いない。だから弟子たちはイエスが納められた墓に行くことができなかった。
そんななか、マグダラのマリアは朝早く墓へと急ぐ。いつの時代も現実と向き合う強さと冷静さは男性よりも女性の方がはるかに勝っているのだ。そこでマリアが目にしたものは、墓をふさいでいるはずの重い石が取り除かれていることだった。
人の手では決して動かしえない大きな石がある。それは自らの弱さとエゴイズムによって招いた罪という石だ。私たちは時としてその石の重さを目の当たりにして、しばし立ち尽くす。どうあがいても動かすのは無理だと思うからだ。マグダラのマリアが見た石は、まさにそれではないか。神と人との間に立ちふさがる動かしがたい隔たりの石。
しかし弟子たちは、マリアによって予想もしなかった事態を知ることとなる。いとも簡単に重い石が取りのけられていたのだ。神と人との隔たりの石は、人の力ではなく、神の憐れみによって取りのけられたのだ。弟子たちがそのことを身に染みて悟るのは、生前イエスと寝食を共にしていた頃ではなく、十字架上でのイエスの死を体験した後のことであった。 いつの時代も人は、時を経て気づくのである。