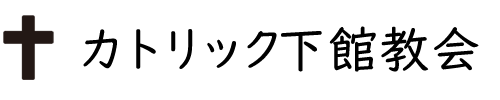傷ある皿
●マタイ4・12-23
カトリック下館教会司祭 本間研二
神父になりたてのころ、教会は天使みたいな善意に満ちた人たちがあふれているパラダイスのようなところだと思い込んでいた。でもそれが錯覚だと気づくのに、さほど時間はかからなかった。当たり前だが教会も欠点や弱さ、そして未熟さをもつ人々の集まりなのだ。だから教会の中には喜びや、憩いもあるが、他者への批判や、互いの心のぶつかり合いもある。
それは決して、現代だけの問題ではない。聖書を開けば、先人たちも欠点や弱さを背負いながら生きた人々であり、決して完全ではなかったことに気がつくのである。
パウロは、自分が伝えようとしているイエスと、その福音に対して絶大な信頼と誇りと揺るぎない愛情をもっていた。しかし、すばらしい宝であるイエスを伝えようとする自分は、弱く、もろい、ひび割れた皿に過ぎないと自覚していた。しかし同時に、傷のある器だからこそ、主に求められるのであり、不完全な皿こそが偉大な神の力が盛られるのに最もふさわしい器であると信じて疑わなかった。
私たちは逆に思っている。神を伝えるためには自分という器は立派で魅力的な方が良いと考え「自分が魅力的で立派ならば、もっと神さまを伝えられた。立派でない自分は、イエスを伝える器にはなれない」と考えてしまう。しかしパウロはそうは思わない。弱く、もろく、欠けている土の器こそが、イエスを最高に伝える道具となれるのだと断言する。なぜなら器は、立派になればなるほど、本来の役割は果たせなくなるからだ。
実家には頂き物の高価な皿が何枚かあった。ときどき出して使おうと思うのだが、結局いつも見るだけで使うことはなかった。万が一落としたらどうしよう、ぶつけて割ったらどうしようと躊躇してしまうからだ。もしその皿に料理が盛られて出てきても、皿にだけに気を使い、料理の味は二の次になってしまうだろう。また皿が「私はきれいでしょう。私は高価なのよ」と自己主張して料理をじっくりと味わうことなどできなくなるかもしれない。それならばいっそのこと、いつもの使い慣れたセルロイドの皿のほうが気兼ねなく、ゆっくりと料理を味わえるというものだ。
人も同じで、自分が立派で優秀で魅力的だと思う人間は、イエスではなく「自分だけを見て」と主張しだすだろう。
ガリラヤ湖のほとりで、イエスに呼ばれて勇んで従った弟子たちだが、聖書にはいたるところに不甲斐ない彼らの姿がある。嵐の湖でイエスを見失いオロオロと立ち往生する弟子たち。鶏が3度鳴く前にそんな人など知らないと拒み、イエスを見捨てた弟子たち。イエスにペトロ(岩)と言う名をもらいながら、岩のように動じない人にはなれなかったペトロ。
欠点や弱さ、やもろさを持った弟子たちは、まさにひび割れた土の器であり、傷ある皿だったのだ。だが自らの不完全さを身に染みて知っていた彼らだったからこそ、師の愛を知った後は最後までイエスを運ぶことができたのだ。
イエスに従うことを選んだ私たちも、高価で立派な皿である必要はない。ひび割れがあっても欠けていてもいい、そんな傷ある皿だからこそ、イエスを世界の隅々にまで届ける「福音の配達人」になれるのだと、私は信じたい。