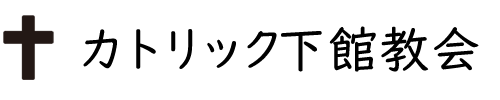光が輝きだすためには
カトリック下館教会司祭 本間研二
●マタイ5.13-16
以前に中高生に聖書を教えていたことがあった。少しでもキリスト教を理解してもらおうと、前もって解説書や文献を読み、授業の進め方も万端整えて私なりに頑張って準備をした。そんな涙ぐましい努力をして、一学期最終日に書いてもらった感想文には「難しくてよく分かんな~い!」「白板に書いた字が汚なすぎ!」「おやつの賞味期限が切れてたぞ!」とボロクソです。
7年間も神学校で積み上げた勉学も、持っている様々の資格も、小教区での経験も、子どもたちの前ではまったく通用しないのです。まさに自分が大切に築き上げてきたものが見事に否定され、心が粉々に砕ける体験でした。
聖書を開いて見ると、あの大聖人パウロも同じような体験をしたようです。パウロは胸を張り誇らしげに語ります。「私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の儀については非のうちどころのない者でした」(フィリピ3.5-6)と。
パウロの学歴、職歴、資格は当時ユダヤ人としては超一流のものでした。しかし、そんなエリートのパウロが誇っていたキャリアをイエスはいとも簡単に粉砕するのです。きっとイエスはこんな風に言ったのでしょう。「パウロよ、お前の履歴書も実績も素晴らしいのは分かる。でも私が求めるのはそれじゃないんだよ」と。きっとパウロの自尊心は音を立てて崩れていったことでしょう。
このイエスとの出会いによってパウロは、今までの職歴や資格などまったく無意味な世界と出会うのです。それは自分との「決別」であり「死」を意味しました。のちにパウロはこう言います。「私は洗礼によってキリストと共に葬られ、その死にあずかるもののなりました」(ローマ6.4)。パウロにとってイエスとの出会いとは「死」を体験することだったのです。それは今までの自分がまったく通用しない世界への誘(いざな)いであり、圧倒的な何者かの力で生かされていたことに気づく「目覚めの体験」でもあったのです。
他者よりも抜きんでた材料を数多く持っていたパウロでしたが、イエスはパウロが誇ろうとするそれらのものを「何それ?」と突き放します。パウロはそこで自らの死を体験します。そしてこの死の後にイエスから一つの答えをもらうのです。「いいかパウロ。人々はお前の知識や職歴を欲しているのではないない。ただ愛して欲しいのだ」と。
子どもたちが私に求めたのも、私の聖書解釈や感動的な話ではなかったのです。ただ愛情を欲したのです。それに気づかない私は、ただ独りよがりに知識をひけらかし、感動させよう躍起となっていたのです。
「死」の後に「愛」が生まれてくる。愛とは持っている物を提供することでも、感動を与えることでもない。持っているものがすべて通用しないと分かった時、私の自我が死ぬ時に初めて輝きだすものなのだ。「世の光」とは、きっとそんな光のことに違いない。