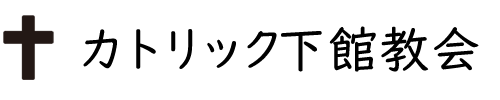ひそやかな月のあかりに
カトリック下館教会司祭 本間研二
●ルカ15・1-32
夏になると川沿いの土手下からは花火が打ち上げられ、大勢の見物客でにぎわっていた。川に近い教会は花火を見る絶好のスポットであり、その日には庭にゴザを敷き、それぞれが持ち寄った料理を食べながらひと時を過ごすのが、教会の夏の恒例行事となっていた。
咲き乱れる花火の美しさに時の経つのも忘れ、気がつけばいつしか終宴となり、心地よく酔った私たちは、腰を上げ食器や空き瓶の片付けを始めた。敷かれていたゴザをクルクル巻きながら私は何気に空を見上げた。数分前まで美しく染まっていた空は、墨を流したように暗かった。その闇の片隅にぼんやりと光が見えた。柔らかな月のあかりだった。月はずっと前からそこにいたはずなのに、鮮やかで刺激的な花火にだけに心を奪われていた私は、月のあかりに気がつかなかったのだ。温かな月の光が、私の心に沁みた。
日々の生活の中で様々な出来事が私たちの前に立ち現われ、心を揺さぶり、刺激し、魅了する。それは喜びや楽しみであったり、苦しみや悲しみであったり様々だが、絶え間なく押し寄せる刺激は、目の前で炸裂する花火のように私たちの心を釘付けにする。私たちはその花火に心奪われ、憔悴し、時としてそれが心を満たしてくれると思い込む。だが身近で上がる花火は刺激的で束の間は現実を忘れさせてくれるが、心を温めてはくれない。いつしかその温かさが錯覚だったと悟り落胆する。私たちの心を本当に温めてくれるものはいったいどこにあるのか。あの温かな月の光はどこにあるのか。
父から財産をもらい家から出て行き、後に「放蕩息子」と呼ばれる男は、どこにでもいる一人の若者であり、私たちの分身でもある。私たちがそうであったように彼もまた、色鮮やかな花火に心を奪われたのだ。刺激的で鮮烈な花火の中に心を満たす真実があると信じ、それが永遠に続くと思ったのだ。その光こそ自分に喜びを与えてくれると思ったからこそ追い求め、のめり込んでいったのだ。だが、やがてそれが幻想だと気づいた。
今まで色鮮やかだった目の前は、花火の日と同じように一瞬にして闇となった。その時、若者は初めて気がついたに違いない。刺激的な光のはかなさと遠くで見つめるあたたかな父の姿に。若者は我に返って言う「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても、罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません」(ルカ15.21)と。若者が色鮮やかな花火に心奪われていた時、父は子を見捨てていたのではない。どんな時も父は子を見守っていたのだ、あの月のように。
〝神の愛〟は月のあかりのようだ。それは鮮やかでも刺激的でもない。いつもひそやかで決して押しつけることはしない。そのあかりは、日々の生活の中の多くの刺激に覆い隠されて見えない。だからこそ私たちは時々立ち止まり、目を凝らし遠くを見なければならない。見上げた先にこそ本当の光がある。それこそが父の心、私たちを包むあたたかな神のまなざしなのだ。