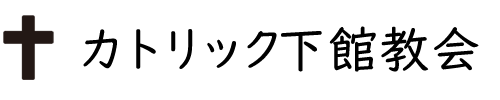死者の月に想う
カトリック下館教会司祭 本間研二
●ルカ11・35.36
神学校を卒業して初めて赴任した教会でのこと、勇んで着任してはみたものの、いったい何をやったら良いのか分からず、途方に暮れる日が続いた。見かねた主任司祭が私に言った。「信徒の方が何人も入院しているので、病院にご聖体を持って行きなさい」。・・・その日から病床訪問の日々が始まった。
Fさんに初めて会ったのは、そんな病床訪問でのことだった。ベッドに横たわるFさんは見るからにやせ細り病状の深刻さを示していた。「こんにちは。このたび教会に赴任しました本間神父と言います。ご聖体をお持ちしました」。そんなぎこちない私をFさんは優しく微笑み迎えてくれた。お祈りと聖体拝領が終わりパイプ椅子に座った私に、Fさんは言った「神父さま、私の病気は癌です。私は医者ですから末期だという事も分かっています。でも来週、私は退院します。最後の時間を自分の家で過ごしたいのです。そこで神父さまにお願いがあります。時間のある限り私の家でごミサを捧げてほしいのです。日々私は弱っていくでしょうし、きっと意識も無くなるでしょう。でもそうなっても私のベッドの傍らでミサを捧げてほしいのです」。Fさんの真剣な願いを私は承諾した。
その日から間もなくしてFさんは退院して自宅へと戻り、私は約束通り毎週訪問して枕もとでミサを捧げた。そして本人が言った通り容態は日に日に悪化し、最初は一枚頂けたご聖体が半分となり、四分の一となり、そのひとかけらも水で浸さないと喉を通らなくなっていった。
でもミサが終わるといつも穏やかな声で「ありがとう」と呟いてくれた。そして間もなくしてFさんの予告通り、何の反応も無い植物人間状態の日が来た。触っても話しかけても反応は無いし、ご聖体も頂けないのだから、もうミサを捧げなくともいいだろう、とも考えた。しかし意識がなくなってもミサを捧げると私は約束をした。その約束を破ることは出来ない。意識のない病人の枕もとで私はミサを捧げた。ミサの度に寝息を立てて眠っている病人の耳元で、私は毎回「Fさん、一緒にミサを捧げましょうね」と大きな声で叫び掛けた。すると右の手がゆっくりと動き出した。震える手は上手く十字を切ることは出来ないが、でもそれは紛れもなく十字を切ろうとする動作に違いなかった。それが終わるとまた穏やかな寝息が続く。そしてミサの途中「Fさん、主の祈りを唱えましょう」と耳元で叫ぶと寝息がぴたりと止まり、言葉にはならないが何かを必死に唱えようとする呻きが喉元から溢れ出るのだった。
あの時の十字架ほど力強い十字架を見たことはない。あの時の「主の祈り」ほど「美しい主の祈り」を聞いたことはない。
地位も名誉も財産もはぎ取られ、家族さえも立ち入れず命が尽き果てようとする時なのにFさんの姿は、途方もなく美しかった。
ほんとうに輝いている人、それは元気に働く人でも、何かに打ち込んでいる人でもない。肩書がたくさんある人でも、有能な人でもない。それは愛されている人。月が太陽の光を反射するように、誰かから愛されている人は必ず身体が発光する。誰かからの愛を知った人は、自然と輝きを放ち始める。親から愛されている子どもは少々いたずら好きでも、明るく周囲を照らす。愛を知らなかった子どもはどんなにまじめな良い子でも、やりきれないほど暗い。
病床のFさんは、かつては元気に働いていた。しかし今、まったく働けずに寝たきりになった。そこには肩書も有能さも通用しない、輝きとは無縁とも思える、死を待つだけの闇の世界が広がる。
だがFさんは輝いていた。神を信じ、神の愛を知り、愛の光を反射して見せてくれた。その輝きは暗闇にいた私の足もとを懐中電灯のように温かく照らしてくれた。懐中電灯は、他者の足もとを照らすために光る。自分自身が注目を浴びるために光る懐中電灯はない。愛の反射による人の輝きも、同様に他者を照らすためにのみある。病床のFさんも、自らに注目を集めるためではなく、周囲の人々を照らし、進むべき道を指し示すために、最期に美しく発光したのだ。
Fさんが天に召されたとき、主のことばが彼に語り掛けるように、私の胸の中で響いた・・・「Fよ、来たれ我がもとに、休ませてあげよう。お前は最後まで、私のことばを生き抜いたのだから」。