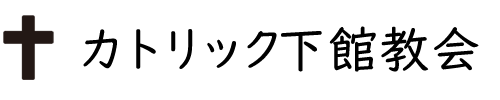「落ち穂」のある人

カトリック下館教会司祭 本間研二
●ルカ19・1-10
フランソワ・ミレーの絵画〝落ち穂拾い〟が好きです。夕暮れの麦畑で腰を屈めて落穂を拾い集める3人の婦人たちが描かれていますが、19世紀初頭のフランスの農村では、こんな光景も珍しくなかったのでしょう。
しかし描かれている婦人たちは、この畑の持ち主ではなく、雇われている労働者でもないそうです。彼女たちは、その日の食べ物にも事欠く貧しい人々であり、生きるために他人の畑に入り、刈り残された〝落ち穂〟を拾っているのです。
旧約聖書には613の掟がありますが、その中の一つが「レビ記」に収められています。そこには「穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽してはならない。収穫後の落穂を拾い集めてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかなければならない」
(レビ19.9-10)とはっきりと記されているのです。
当時のフランスの農村では、旧約聖書の掟がまだ人々の中で受け継がれ、守られていたのでしょう。
誰かのために自分に権利あるものをそっと差し出す〝落ち穂〟・・・しかし、私たちの周りに〝落ち穂〟はあるのでしょうか。収穫後の畑を見れば、機械で綺麗に刈り取られ、一粒の落ち穂も見つけることが出来ません。
同じように、今の時代では「自分のものは自分のもの」という風潮が当たり前となり、人の情けや思いやりという〝落ち穂〟など、私たちの周りのどこを見渡しても見当たりません。
中学2年生の頃だったでしょうか、どうしても学校に行くのが嫌になった時期がありました。いじめがあった訳ではありません。仲間はずれになった訳でもありません。担任の先生との心のズレがいたたまれなくなったのです。先生は暴力的とか、えこひいきをする人ではありませんでした。ただ自分の正しさをいつも強要する人でした。自分の思う正しさ以外は、すべて跳ね返す人でした。だんだんと私にとって教室は息苦しい場所となっていきました。何とか学校には行けても、校舎に入った途端に心は教室に行くことを拒絶するのです。
そんな私にとっての避難所は保健室だけでした。そこには生徒たちからババやんと呼ばれる小柄で赤いメガネをかけた保険の先生がいました。
私は保健室に、ある日は頭が痛い、ある日は腹が痛い、ある日は足が痛いと病気や怪我を装い通いました。そんな私をババやんはいつも微笑んで迎えてくれました。
具合が悪いといって行くのですから、最初はベッドに横たわりますが、身体はどこも痛くはないですから5分もすると退屈になり起き上がりベッドに腰掛けます。するとババやんは仕事をしている手を止めベッドの側にあるパイプ椅子に座り、私の取り留めのない話を聞いてくれました。子供の話ですから楽しいはずはありません。でも最後まで聞いてくれ必ず決まって、私の肩をポンと叩いて「大丈夫、大丈夫」と笑顔で言うのです。
そんな日が10日ほど過ぎた頃でしょうか、その日もベッドに腰掛けて話し終えた私に「もう大丈夫だね!」とやさしく声をかけ、背中をそっと押してくれました。そのババやんの声に励まされるように私は自然に教室に戻れるようになったのです。
ババやんは最初から私が仮病だと分かっていたのです。なぜなら腹が痛くとも、頭が痛くとも、足が痛くとも、飲ませてくれる薬はいつも正露丸一粒でしたから。
ババやんは私の仮病を見抜いていたのですから「あなた仮病でしょ。早く教室に戻りなさい」と言うことも、私の存在を無視して自分の仕事をすることもできたのです。でもババやんは仮病と知りながら、黙って私の話を聞いてくれたのです。自分の時間を裂いて、痛む私の心にそっと寄り添ってくれたのです。
今になって気づくのです。あの保健室での時間こそ〝落ち穂〟だったのだと。あの微笑みこそババやんが私のためにそっと置いてくれた〝落ち穂〟だったのだと。
ザアカイは、機械で刈り取るように、人々から一粒も残さずに取り立てていたのです。「自分の物は自分の物、それのどこが悪い」。そう信じて生きて来たのです・・・でもそれが本当ではないと薄々気がついていたのでしょう。なぜなら、いくら働いても喜びがないからです。〝罪〟には喜びがありません。
愛ある〝落ち穂〟は、受ける人にも、与える人にも喜びを与えます。
ザアカイはそのことに気がつき、胸を打ちながら言います。「神さま、罪人のわたしを憐れんでください」と。
時々自問自答します。「信仰者とは何者か?」と。ファリサイ人のように、ただ盲目的に神を信じ、熱烈に祈り、形式的に掟を守り、知識のみ聖書を学び、己の正しさを強要する人のことでしょうか。否、信仰者とは〝さり気なく落ち穂を落とす人〟でしょう。