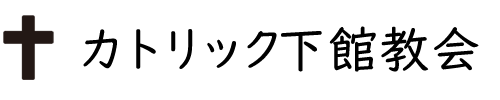裸のままで
カトリック下館教会司祭 本間研二
●マタイ18.21-35
初めて聖書を読み始めた頃、聖書の中に様々な発見と驚きを覚えた。心が潤され、新しい景色が次々と眼前に広がっていくようだった。しかし時が経つにつれ最初の感動も徐々に薄れ、新鮮だった言葉も心に響かず、イエスのメッセージは素晴らしいと思うのだが、それを実行できない自分がいた。読むほどに落ち込み、しばし聖書を開くことはなかった。それは聖書に飽きたのか、それとも自分には手の届かない理想の世界と感じたからなのか。
今思えば、聖書が「手の届かない書物」となったのは、そもそも私の聖書への接し方、読み方が間違っていたのだ。つまり私は聖書を「克己」の書として読んでいた。「克己」とは、自分の弱さを退け、誘惑を撃退し、己に克つ(勝つ)と言う意味だが、若かりし頃の私は、弱さに追い詰められ、苦しみを一人で抱え、より強い自分になろうともがいていた。そんな苦しみを乗り越えるには、強い自分になり頑張るしかない。苦しみや災いも頑張って努力すればきっと乗り越えられる。だから歯を食いしばって頑張ろう、と考えていた。
この思考は日本人一般には馴染みやすいものであり、日本人の美徳の一つでもあるのだが、何でもすぐに「克己心」を持ち出すのは少々問題でもある。
私たちは時として頑張る材料として「聖書」を用いていないだろうか。「神の掟をすべて守る自分であらねばならぬ」と。そうならば要注意だ!聖書は私たちの「克己」に奉仕する書物ではない。聖書に登場するのは強者ではなく、弱さも醜さもさらけ出して神にすがる裸の人間たちだ。その意味で聖書は、苦しみを「克己」ではなく「神との交わり」によって乗り越えようとする書物なのだ。固い殻の中に入り身を守るのではなく、恥も罪もさらけ出しながらも神と繋がることによって、したたかに成熟する人間を描いている。イエス自身も生涯で最も苦しい時に強い姿に変身するのではなく、傷つきやすい裸のままの自分を愚直に天の父に差し出した。
もしも聖書を「克己の書」として読むならば、私にはイエスの言葉は重すぎる。七の七十倍も赦し続けていくには強靭な精神と肉体を作り上げ、挙句の果てに自らの心を極限まで追い詰めねばならない。しかも赦したくても赦せない自分を駄目な人間として責めてしまうでしょう。これでは底なしの自己険悪に陥り、聖書は恐怖の本となってしまう。そうではなく聖書の言葉からイエスとの対話が始まればよいのです。
「七の七十倍赦せって。そんなこと無理ですよ。だって私がどんなにひどい目に遭ったか知らないでしょう。殺したいほど憎い人がいるんですよ。ねぇ、聞いてくれます!」。イエスはきっと喜んで聞いて下さるに違いない。だってそうやって聖書は作られ、伝えられてきたのですから。延々とつづく神との会話こそが、人をいつの間にか平和のステージへと招いていくのでしょう。
新しく始まった2022年も気負うことなく、裸の心でイエスとの交わりを深めていけたらと思っています。